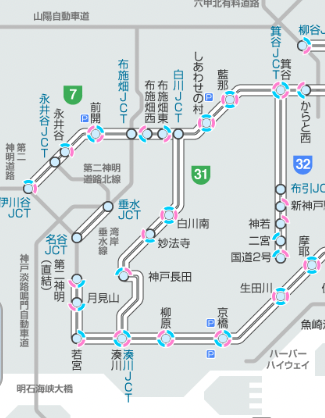1時に寝て7時に起きた。タスクが溜まり過ぎてそろそろ辛くなってきているところ。この余裕の無さはよくないことなので、自分のダメさ加減というか、大いに反省しないといけない。
隔週の雑談
顧問のはらさんと隔週の打ち合わせ。いつもは打ち合わせの議題を2-3日前には共有するようにしている。だいたい水曜日前後に議題のリファレンスをはらさんに共有して金曜日の朝に話している。しかし、今週はリファクタリングに集中し過ぎていて前日の寝る前になって議題を共有していないことに気付いた。そして朝起きてから急ぎで議題を考えて共有していた。これはとてもよくない。準備ができていないので今日の議題は主に近況の話しをしていた。
ハドルの雑談
先日から 午前中はハドルに滞在 するようにしている。今週は木曜日にチーム外から勉強会についての相談が、今日はメンバーから気分転換に雑談にやってきてくれた。おそらく私がハドルにいなかったらゼロだったコミュニケーションの機会が、1週間に1-2回でもあることに私は嬉しく思ってしまう。フルリモートワークにおける、オフラインのような気軽な雑談の機会を提供する施策の1つとして意味なくハドルに入るのは悪くない気がしている。そのときにコミュニケーションを強制させるような押し付けが発生しないよう、運用ルールを徹底することが大事に思える。いまは相手がハドルに入ってくると 1on1 のような雰囲気になってしまうのでその次の挑戦としてはハドルに入っていても話さなくてよいといった運用ルールを設ければよいのではないかと思う。例えば、午前中はとりあえずハドルに入って気分が向いたときだけ話しかけるみたいな、ゆるいコミュニケーションの場になればいいなと思う。
ハドル雑談の運用ルールのアイディア
- ハドルに入らなくても業務上の支障は一切おきない
- ハドルにいる人には、用事があってもなくても、話しかけてよい
- ハドルに入っていても話さず聞いているだけでもよい
- 業務に集中していて忙しいときは話しかけられても後回しにしてもよい (ハドルから退出した方がわかりやすいかもしれない)
go の generics 勉強会
ちょうど先週からあちこち直したり、mongodb のクライアント周りをリファクタリングしたりしている。その過程で generics を使ってコードの共通化もしたりしている。私自身 generics で意図した通りにコンパイルできなくてはまってしまった事例もあるのでそういった失敗コードも共有した。go の generics はコードに対して静的な領域しか適用されず、コード中における動的な値の型は generics とは直行した概念だというところに初学者ははまるのではないかと思う。私がはまった。参加者におそらく1度はまるからはまったときに私が話していたことを思い出してとコードの解説をしていた。
今日は type constraint でできることと動的な値との関係を混同して generics でできないことを一生懸命やろうとしてた。interface に変換して型パラメーターに type assertion すればコンパイルは通る。2時間ほどはまってた。。。https://t.co/vmk6CfVTl8
— Tetsuya Morimoto (@t2y) February 16, 2023
余裕があったらスライドにまとめて後で資料として再利用できるようにしたかったものの、私の作業に余裕がなさ過ぎて次のリファレンスから引用しながら解説するといった勉強会になった。ただ私が読んでよいと思った他者のスライドやブログの記事のみを紹介している。それはそれで参考にはなるので勉強会の意図としては問題なかったんじゃないかとは思う。