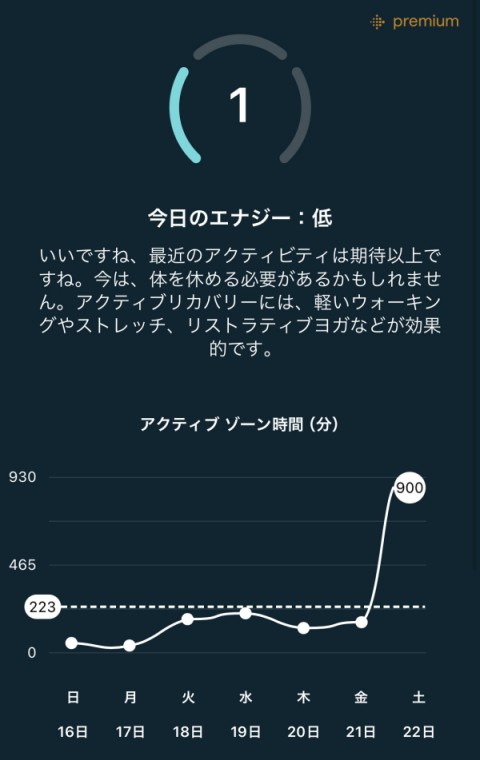今日は荷解きしていたので運動はお休み。収納はたくさんあるものの、まだ部屋に不慣れで使い勝手がわかってないからどこに何を入れるか、決まらなくてなかなか進まない。
gitlab ci/cd のセキュリティ対応
gitlab のアクセストークンが 16.0 以前までは無期限に利用できたのが最長1年の有効期限が設定されるようになった。16.0 移行で無期限のアクセストークンは移行後から1年の有効期限となる。
gitlab ci/cd のジョブでパッケージレジストリの操作が、これまでは ci job token (ジョブ実行のタイミングで自動生成される短期間有効なトークン) でアクセスできなかった。そこに project access token を発行して組み込んでいた。しかし、そのトークンが1年ごとに有効期限切れするようになったら保守コストがかかるからこれをやめたい。調べてみると、ちょうど ci job token も進化して 16.1 以上でパッケージレジストリへのアクセスができるようになった。
移行の注意事項として project access token は PRIVATE-TOKEN というヘッダーを使うが、ci job token は JOB-TOKEN というヘッダーを使う。curl なら次のようにして project access token を使わなくてもよくなった。
$ curl --fail-with-body -s -H "JOB-TOKEN: ${CI_JOB_TOKEN}" ...
しかし、ci job token でリポジトリへの push はまだできない。これもいま修正中なので 17.2 から対応されるようだ。
社宅既定の作成
家賃計算 を終えて社宅関連の手続きは完了かな?と税理士さんに相談していたら社宅既定を作るのが望ましいと教えてもらった。
うちの会社は就業規則もなく、既定はほとんど作っていないものの、社宅のような特性を、法人と個人の境界を曖昧に運用するのもガバナンス的によくないというのは理解できる。来月あたり時間のあるときにぼちぼち既定を作っていこうと思う。
google マップのクチコミ
社宅探しを手伝っていただいた 不動産仲介会社 さんに感謝を伝える意図も含めて google マップにクチコミを書いた。35レビューで 5.0 しかないということからしょうみさんの信頼の高さが伺える。このままクチコミが増えていくと、しょうみさんの会社がどのように成長していくのか。この先の展望も楽しみにしている。きっと最後はうまくいくと思う。