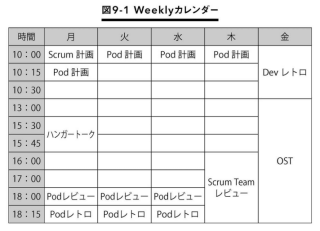23時に寝てこわい夢をみて1時半に起きて、そのまま寝たのか寝てないのかよくわからない仮眠状態で5時半に起きた。
朝活: アジャイル開発とスクラム 第2版
【三宮.dev オンライン】リモート朝活もくもく会 で第10章 竹内・野中のスクラム論文再考を読んだ。1986年に竹内氏と野中氏によって書かれた The New New Product Development Game から得た概念や理論的背景をスクラム創設者のジェフ・サザーランド氏がソフトウェア開発の方法論として体系化したものがスクラムになる。そのため、原点はこの論文にある。第10章ではオリジナルに書かれている内容とスクラム開発を比較している。オリジナルの論文にある TypeC (キヤノンやホンダの新製品開発) のようなチームの特徴として次の6つをあげている。
不安定な状態を保つ
最初に綿密な計画や指示があるわけではない、チームは自由な裁量と同時に困難なゴールを目指す
プロジェクトチームは自ら組織化する
チームは不安定な状態から自己組織化し、対話の中で自律状態を作り出す
開発フェーズを重複させる
開発フェーズを重複させることで、メンバーは専門分野を超えてプロジェクト全体で責任をもつようになる
「マルチ学習」
メンバーはグループ全体として学習し、専門を超えて学習する
柔らかなマネジメント
無管理でも強い管理でもない自主性を尊重した柔らかなマネジメントが重要である
学びを組織で共有する
過去の成功を組織に伝える、もしくは意識的に捨て去る
オリジナルの論文の解説を読んでいると、古きよき日本の家族ぐるみの職場やチームの働き方のように思えてくる。時代が違うのでいまからこういった働き方に戻るのは現実的ではないだろうが、その中で重要だった概念や要素を、いまソフトウェア開発方法論としてのスクラムで実践できるのはいろいろと私の中でも思うことがある。私の考える課題管理の方法論にも竹内・野中氏のオリジナルの論文の概念は影響を受けるように思えた。章末にコラムとしてジェフ・サザーランド氏のインタビュー記事もあった。マイクロファイナンスのプロジェクトを通して、小さなグループに小さくお金を貸し出すことが、貧困から抜けすための小さなきっかけ (ブートストラップ) になるという体験からスクラム開発の動機づけになったという話しは哲学として印象に残った。なにかを成すには哲学が大事だと思う。
データがあると同期したくなる
お仕事でスクラムのふりかえりをやっていて miro と backlog のデータ同期という話題が出た。業務チームはブレインストーミングで要件を洗い出したりする作業のときに miro を使っていて、miro ベースでメモを記述した後でバックログアイテムとして backlog に登録する。このとき backlog に登録した後で miro を捨てるならいいが、残したまま次の展望や要件の洗い出しにも再利用したりしていると、miro と backlog のバックログアイテムの内容が乖離したり不整合が発生したりする。チームとしてはバックログアイテムに書いてある内容が正という運用をしているため、miro のみに最新の情報がある状態が続くと課題になる。私の知る限り、miro と課題管理システムのデータ連携のツールはないと思う。
私からみたら最初からすべてバックログアイテムに文章で書けばいいやんで話が終わってしまうが、人によって使い慣れたツールは異なるため、そんな単純な話しでもない。一方で昔は miro や backlog がなかった時代もあって、そのときは物理的な付箋紙をホワイトボードに張りながら作業をしていたから、本来は同期したいという概念もなかったはずという意見も出た。たしかにツールがデジタルになって電子データとなった瞬間からデータの再利用を考えるようになるんだなと私も思えた。あと付箋紙をホワイトボードに貼り付けていた時代は何週間もその状態のまま放置するといったこともなかったのではないか?という気もした。